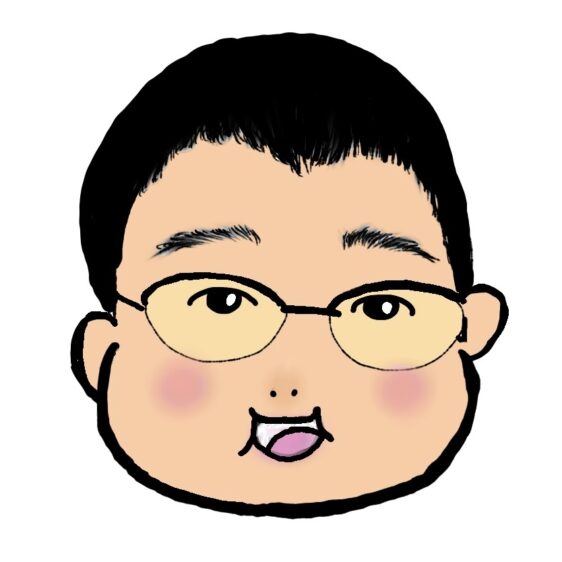 のぞむ
のぞむ「神社」の読み方「じんじゃ」「じんしゃ」?どっちなの?
って、疑問に思っていませんか?



「じんじゃ」? それとも「じんしゃ」? 小学生のあなたがふと疑問に思ったその読み方、実は地域によってちがいがあるんです。
この記事では、「じんしゃ」「じんじゃ」どちらが正しいのかをやさしい言葉でわかりやすく説明します。
さらに、神社ってどんな場所なの?どんな神さまがいるの?などの疑問にもこたえていきます。
この記事を読めばわかること:
「じんしゃ」と「じんじゃ」どっちが正しいの?
地方によってちがうのはなぜ?
神社ってどんなところ?何をするの?
神社に行くとき、ことばのちがいがわかるともっと楽しくなるかもしれません。
ぜひ、読んでみてくださいね!
「じんしゃ」と「じんじゃ」どっちが本当?
「神社」はなんて読むのが正しいの?


「神社」という漢字を見たことがありますか?
これは日本でとても大切な場所の名前で、神さまがいるところです。
この「神社」、ほんとうはなんて読むのが正しいのでしょう?



答えは――「じんじゃ」です!
国語の辞書(じしょ)で調べると、「神社」は「じんじゃ」と書いてあります。
だから、テストで「じんしゃ」って書いたら、まちがいになってしまうかもしれません。
でも、「じんしゃ」と言う人もいます。
それはまちがいなのでしょうか?
それには、ちょっとした理由があるんです。
このあとのお話で、そのわけをやさしく説明していきますね。
「じんしゃ」って聞いたことある?
みなさんの中で、「じんしゃ」って言ってる人を聞いたことがある人はいますか?
もしかしたら、家族の人や、おじいちゃん・おばあちゃんがそう言っているかもしれません。
たとえば、
「初もうでに“じんしゃ”行こうか〜」
「“じんしゃ”の前で写真とろうよ」
こんなふうに聞こえてきたことがあるかもしれません。
でも、学校では「じんじゃ」と習いますよね?
じゃあ、「じんしゃ」はまちがいなのでしょうか?
いいえ、まちがいとは言いきれないんです。
「じんしゃ」は、ある地方(ちほう)や地域では、ふつうに使われている読み方なんです。
どうして「じんしゃ」って言う人がいるの?
日本には、いろんな地方や方言があります。
その中には、「じんしゃ」と読む地域もあるんです。
たとえば、鹿児島県や福岡県など、九州地方では「じんしゃ」と言う人が多いと言われています。
これは、昔からその地域で使われてきた言葉のクセやなまりが影響しているんです。
つまり、「じんしゃ」は、その地方の人にとってはふつうの言い方なんですね。
でも、全国で見ると、「じんじゃ」が正しい読み方とされています。
だから学校では「じんじゃ」でおぼえておくのが大切です。
地方によってちがうの?
はい、その通りです。
日本では、**方言(ほうげん)**といって、地方ごとに言葉の使い方や読み方がちがいます。
たとえば、「ありがとう」を「おおきに」と言うのは関西(かんさい)地方です。
それと同じで、「じんじゃ」を「じんしゃ」と読むのも、地域によるちがいなんです。
なので、「じんしゃ」と聞いても「え?それまちがいじゃないの?」とは思わなくていいんです。
むしろ、「あ、この人はこのへんの出身なのかな?」と考えると楽しいですね♪
じっさいに使われているところを見てみよう
インターネットやSNSなどで「じんしゃ」と検索してみると、たしかにそう読んでいる人がいます。
ある人は、「鹿児島ではじんしゃって言うよ」と書いていたり、
また別の人は、「福岡ではふつうにじんしゃって言うと思ってた」と話していたりします。
また、ニュースサイトや地元の新聞などでも、「○○じんしゃ」と書いてある例もあるんです。
ただし、神社庁や国語辞典では「じんじゃ」が正式な読み方とされています。
なので、「じんしゃ」と言ってもわるくないけど、正式には「じんじゃ」と言うのが正しいということになりますね。
「じんしゃ」と言う人がいるのはどうして?
に進めて本文を作成していきます。
すべての小見出しを順番に仕上げていきますので、少々お待ちください。
それでは、続きを書いていきます。
「じんしゃ」と言う人がいるのはどうして?
鹿児島や福岡では「じんしゃ」って言う?
はい、じつは鹿児島県や福岡県の一部では、「神社」のことを「じんしゃ」と読む人がいます。
これは、その地域の人たちのあいだでは昔からよく使われている言い方です。
たとえば、鹿児島では、
「今日はじんしゃにおまいりに行こうか」
「あのじんしゃは有名だよ」
というように使われることがあります。
もちろん学校では「じんじゃ」と習いますが、地域によっては「じんしゃ」もふつうなんですね。
「じんしゃ」と言ってる人がいても、それはその人の地域の言い方かもしれません。
だから、「まちがい」と思わずに、「そういう言い方もあるんだな」と知っておくと、とても良いですね。
「じんしゃ」はまちがいじゃないの?
「じんしゃ」と言っても、まちがいとはかぎりません。
たしかに、学校や辞書では「じんじゃ」と書いてあります。
でも、その地域でふつうに使われてきた読み方であれば、「じんしゃ」もその地域では正しいと言えます。
たとえば、鹿児島県や福岡県では「じんしゃ」が使われています。
しかし、全国でつうようする読み方としては「じんじゃ」が正しいとされています。
だから、
- 学校では「じんじゃ」でおぼえる
- 地元では「じんしゃ」でもOK
このように使い分けができると、とてもかしこいですね!
インターネットではどう言われているの?
インターネットでも、「じんしゃ」と「じんじゃ」の話はよく話題になります。
たとえば、ある人は、
「じんしゃって言ったら、じんじゃでしょ!って言われた…」
とか、
「え!?うちの地元ではみんな“じんしゃ”って言ってるよ?」
というやりとりをしていたりします。
Twitter(ツイッター)やYahoo!知恵袋などで調べてみると、いろんな地域の人が「どっちが正しいの?」と気になっているのがわかります。
中にはけんかになってしまう人もいますが、本当はおたがいの地域のちがいを知るチャンスなんですよね。
「じんしゃ」と言う人はどれくらいいるの?
「神社(じんじゃ)」を「じんしゃ」と読む人がいるというお話をしてきましたが、実際にそう言う人はどれくらいいるのでしょうか?
じつは、はっきりした数字はわかっていません。
国や神社の団体、辞書会社などが「じんしゃ/じんじゃ」の使われ方について正式に調べたデータは、今のところ見つかっていません。
ですが、質問サイトを見てみると、「じんしゃ」と読む人がたしかにいることがわかります。
たとえば:
- 「鹿児島では“じんしゃ”ってみんな言ってたよ」
- 「福岡のじいちゃんが“じんしゃ”って言ってた」
- 「学校で“じんじゃ”って習ったのに、親は“じんしゃ”って言ってる」
という声が見つかります。
さらに、いくつかのブログやSNSでは、「“じんしゃ”って言ったら“まちがいだよ!”って友だちに言われたけど、本当にまちがい?」という疑問の投稿もあります。
このことからわかるのは:
- 「じんしゃ」と読む人は少ないけれど、たしかに存在する
- 特に九州地方に多いという声が多い
- でも、正式には「じんじゃ」と読むのが正しいとされている
ということです。
ふだんの会話では、地域によって「じんしゃ」もつかわれているけど、学校や辞書では「じんじゃ」が正しい読み方。
それぞれの言い方に、ちがった背景や文化があると考えると、とてもおもしろいですね!
また、神社庁(じんじゃちょう)という神社の本部では、「神社」の読み方は「じんじゃ」が正式だと説明されています。
ですから、まとめると:
| 読み方 | 地域 | 正式な読み方か? |
| じんじゃ | 全国で一般的 | ○(辞書や学校でもこれ) |
| じんしゃ | 九州などの一部 | △(地域ではOK) |
このようになります。
神社ってなにをするところ?
神社はどんな場所なの?
**神社(じんじゃ)**とは、日本に昔からある、神さまをまつっている場所のことです。
神社には、木でできた立派な建物や、「鳥居(とりい)」とよばれる門のようなものがあります。
人びとは、神社に行っておまいりをしたり、お願いごとをしたりします。
たとえば、
- 「テストでいい点がとれますように」
- 「家族が元気にすごせますように」
- 「けがをしませんように」
などのお願いをする場所が神社です。
また、お正月や七五三、運動会の前など、いろいろな行事のときに神社へ行くこともあります。
神社は、みんなのねがいを神さまにとどける場所なんですね。
神社とお寺(てら)と、どうちがうの?
神社とにている場所に、「お寺(てら)」があります。
でも、神社とお寺は、ちがうものです。
| 比べること | 神社 | お寺 |
| いるのは? | 神さま | 仏さま(ほとけさま) |
| 入り口にあるのは? | 鳥居(とりい) | 山門(さんもん) |
| まもってくれる人 | 神主(かんぬし) | お坊さん(ぼうさん) |
| おまいりの作法 | 2回おじぎ、2回手をたたく | 手を合わせて合掌(がっしょう) |
| おまいりの時 | お正月、七五三など | お盆、法事など |
このように、まつっているものも、やり方もちがうんです。
神社とお寺のちがいを知ると、もっと日本のことがよくわかりますね!
神社にはどんな神さまがいるの?
神社には、いろいろな神さまがまつられています。
たとえば、
- 勉強の神さま「菅原道真(すがわらのみちざね)さま」
- 商売の神さま「えびすさま」
- 家を守ってくれる「天照大御神(あまてらすおおみかみ)さま」
- 交通の安全をまもる神さま
などなど、それぞれの神社によってまつっている神さまがちがいます。
どの神さまも、日本の昔ばなしや歴史に出てくる大切な存在です。
神社に行くときは、「どんな神さまがいるのかな?」としらべてみると楽しいですよ。
神社にはどんなときに行くの?
神社に行くのは、つぎのようなときが多いです。
- お正月(はつもうで)
- 七五三(7さい・5さい・3さいの記念)
- 受験(じゅけん)の前に合格きがん
- 運動会や行事のまえに安全をいのる
- 旅行のとちゅうに立ちよる
また、「パワースポット」として人気のある神社もあります。
これは、「元気や力をもらえる場所」として知られているところです。
神社は、ただの建物ではなく、心が落ち着く場所でもあるんですね。
日本には神社がいくつあるの?
日本には、なんと8万社(しゃ)以上の神社があります!
これは、コンビニの数よりも多いとも言われているんです。
全国の町や村、山や森の中にも神社があります。
つまり、どこに行っても神社があるということですね。
それぞれの神社には、長い歴史があるところも多く、昔の人たちが大事にしてきた場所です。
旅行に行ったときなどに、ちょっと神社に立ちよってみると、新しい発見があるかもしれませんよ!
まとめ:「じんしゃ」と「じんじゃ」どっちでも大切なのは、気もちです
ここまで、「じんしゃ」と「じんじゃ」のちがいや、神社についてやさしく説明してきました。
まとめると、こうなります:
- 「神社(じんじゃ)」が正しい読み方
- 「じんしゃ」も一部の地域ではふつうに使われている
- 地方によって言葉の使い方がちがうのは、方言だから大丈夫
- 神社は神さまがいる場所で、おまいりの作法やマナーも大切
- 秋田県にも、すてきな神社がたくさんある!
いちばん大事なのは、「まちがってる!」と人を否定(ひてい)することではなく、
ちがいを知って、やさしい気もちでおたがいを大事にすることです。
「じんしゃ」と言う人がいても、「あ、それ方言かもしれないね」と、やさしくうけとめられる人になれたらすてきですね。
そして、神社に行ったときは、神さまに「ありがとう」と「これからもよろしくね」の気もちをこめて、心をこめたおまいりをしてみてください。
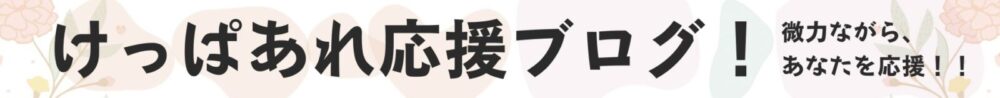


コメントはお気軽に!