最近、「馬車馬のように働く」「馬車馬のように働いて働いてまいります!」というフレーズがSNSやニュースで話題になりました。
なんだか昔っぽい?それとも熱い気合?……と賛否両論。でも、今の私たちにとって「働く」とは一体どうあるべきなのでしょうか。
 かなえ
かなえワークライフバランスという言葉が浸透する今、この発言をきっかけに“働き方の常識”をゼロから見直してみませんか?
本記事では、「馬車馬のように働く」の意味や由来から、言葉の使い方、現代の働き方の工夫、スマートな言い換え、ワークライフバランスの考え方、そして話題の発言への考察まで、中学生でもわかる優しい言葉で徹底解説。
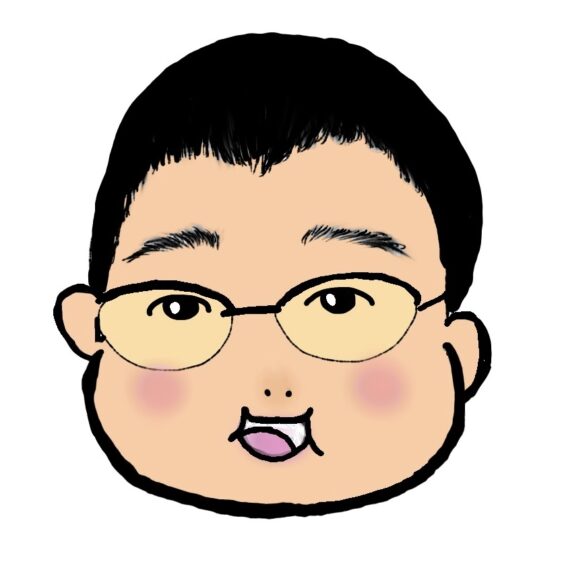
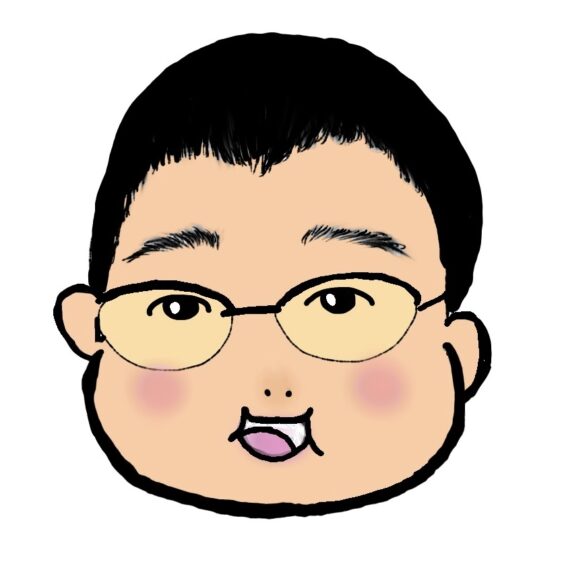
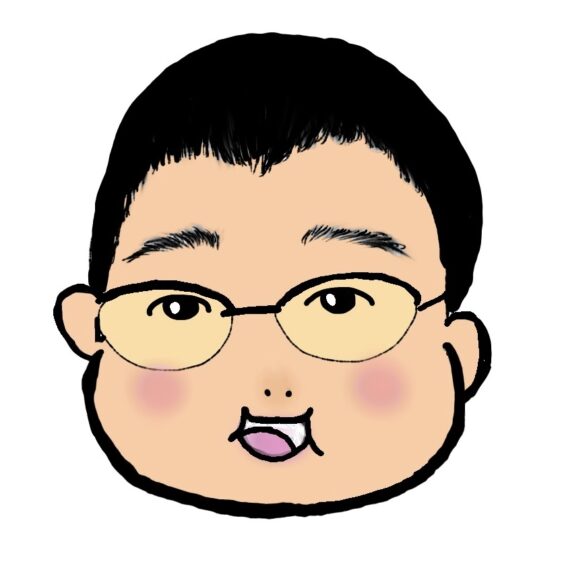
これからの時代にふさわしい、自分らしい働き方を一緒に考えていきましょう!
1章:悩みを秒速で解決:「馬車馬のように働く」より“WLBとは”で整える
毎日、仕事量が山のようにあって、家に帰っても頭の中が「やることリスト」でいっぱい。睡眠も足りない、趣味も疎か。そんな毎日を「しょうがない」で片づけていませんか?その悩みを、まずは “設計の力” で軽くする方法を見ていきましょう。
WLBとは何?まず概念をつかもう
“WLB” は「ワークライフバランス」の略で、ただ残業を減らすことではありません。仕事の責任をしっかり果たしながら、人生側でやりたいこと・やるべきこともある程度実現できる状態を指します。
内閣府の定義にも
「仕事と生活が両立できる状態」
— 引用:内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の定義」より引用
などの表現があります。
この意味を押さえると、「もっと働け」「とにかく時間を増やせ」という旧来型の発想とは逆の軸が見えてきます。
“境界線の設計”がまず武器になる
量を減らす前にやるべきことは、「境界線を決めること」。仕事とプライベートの切れ目を設計することが意外と効くのです。
たとえば:
- 時間の線を引く
「〇時まで仕事」「それ以降は見直しのみ」などをルール化。例外を事前に共有しておく。 - 空間の線を決める
在宅勤務なら、専用のデスク・椅子を用意し、寝室やくつろぎスペースとは物理的に区別する。これにより、「仕事モード ⇄ 休みモード」の切り替えスイッチが働くようになります。 - 通知・通信のルールを設ける
チャット・メール・メッセージは「確認時間をまとめ読み」や「深夜は通知オフ」など時間帯制限をする。既読=即レスの暗黙の圧を自分で制御することも大切です。 - 依頼・指示の基準を明文化する
仕事を頼むときは「何を、どこまで、いつまでに」の三点を明示する。これが曖昧なままだと、依頼側と受け手で期待がズレ、無駄や摩擦が生まれます。
こうした設計は最初はぎこちないかもしれませんが、半年も続ければ線を引くことそのものが“思考の筋力”になります。
疲れを減らす3つの戦略的習慣
境界線を設計したら、そこに支えを与える3つの習慣を取り入れましょう。これらはどれも時間をかけず、すぐ実行できるものです。
- 定時睡眠・起床の固定
起床・就寝の時間を毎日同じように近づけることで、体内時計が整います。スマホをオフにするルールもセット化するのが効果的。 - “宣言タイム”の導入
朝に「今日この時間以降は通知オフ」などをチームや家族に伝える。口に出す/書くことで、自分自身と他者へのプレッシャーを調整できます。 - 戦略的小休憩の挟み込み
仕事を“連続でやり切る”よりも、50分集中+5–10分休憩など短いブレイクをはさむ方式(ポモドーロなど)を前提に作業設計をする。立ち上がる・ストレッチ・水を飲むなど、体を動かす休憩が効果的。
これらの習慣を日常化することで、「やることが多すぎて圧倒される感じ」は徐々に薄れていきます。
チェック:あなたの“無形の枷(かせ)”を探せ
以下のチェックリストを使って、あなたの無意識の“枷”がどこにあるか確かめてみてください(該当すれば改善の糸口)。
- 夕方以降もメール・チャット通知が来る
- 家に帰っても仕事の“やること”が頭から離れない
- 会議に目的が明示されていないことが多い
- 依頼を受けた内容が曖昧なまま作業を始めてしまう
- 夜中に「明日これやらなきゃ」が頭を占領する
いくつ当てはまるかで、「改善すべき壁」が見えてきます。これをもとに、第2章以降での具体的な言葉の扱い・仕組みづくりへつなげていきます。
2章「馬車馬のように働く」とは?意味・由来・読み方をスッキリ解説
「馬車馬のように働け」──このフレーズ、なんだかすごい圧を感じませんか?でも本来、どんな意味なのでしょう?古くから使われているこの比喩には、実はちょっと切ない背景もあります。
ここではまず、「馬車馬のように働く」の正確な意味・読み方・語源を確認し、その後でなぜそれが“失礼”と言われたり、“女性”に向けて使われると問題が生じやすいのかについて解説していきます。
「馬車馬のように働く」の読み方・意味・語源
まず、読み方は 「ばしゃうま」。音だけだと読みづらいですが、辞書にも記載があり、正しく読めるとスマートな印象になります。
意味は以下のように説明されています:
「馬車馬のように、わき目もふらず働き続ける様子」
─ 出典:小学館『デジタル大辞泉』(コトバンク掲載)
https://kotobank.jp/word/馬車馬のように働く-645844
つまり、目的だけに集中してまっすぐ働き続ける、まさに“力仕事の代名詞”のような言葉です。
語源(由来)は、実際に馬車を引く馬が視界を制限され、左右が見えないように「ブリンカー(目隠し)」をつけられていたという現実から来ています。この馬はただひたすら前に進むことしかできないのです。
「馬車を引く馬には、視界を制限するための目覆いがつけられていた。そこから、“わき目もふらずに働く”という意味の比喩として使われるようになった」
─ 出典:語源由来辞典より https://gogen-yurai.jp/bashauma/
このように、“馬車馬”は一見たくましい働き者のようですが、自由がなく、コントロールされ、休まず働かされる存在でもあります。
なぜ“失礼”と言われるのか?
「馬車馬のように働いて」──というフレーズ、上司や先輩から言われたらどう感じますか?「よし、やってやろう!」と思える場合もありますが、多くの人が感じるのは プレッシャー や 雑な扱いをされたような感覚です。
この言葉が失礼にあたるケースは以下のような場面です:
- 相手の努力を認めず、「働け」という命令形として使うとき
- 体調や事情を無視して一方的に負荷をかけるように使うとき
- 公の場やフォーマルなスピーチで不適切な比喩として用いたとき
例えば、上司が「馬車馬のように働いてもらう」と部下に言えば、本人の気持ちや体力・事情を無視して、単なる“労働力”として扱われた印象を与えかねません。
特に令和以降の働き方改革・ダイバーシティ推進の時代には、「本人の尊厳を傷つけない言葉選び」が求められています。ですので、仮に“全力で頑張ってほしい”という気持ちだったとしても、馬車馬という表現は相手を道具のように感じさせる可能性があるのです。
“女性”に向けて使うときの特別な配慮
この言葉が女性に対して向けられる場合、さらに慎重な配慮が必要です。というのも、現代でも家庭と仕事の両立に苦労している女性は多く、「仕事も家事も育児も全部こなす」ことを求められる場面が少なくありません。
そんな中で「馬車馬のように働け」と言われると、「またか……」という疲労感・閉塞感を与えてしまうのです。
実際に、女性が働きやすい職場作りとして以下のような対応が求められています:
- 育児や介護との両立に配慮した勤務体系(時短・フレックス・リモート等)
- 成果ベースでの評価制度(時間でなく中身で評価)
- 上司の理解ある言動(「もっと働け」ではなく「どうすればやりやすいか?」)
現代の職場では、“量”で評価する働き方から、“質と工夫”で評価する働き方へと大きく価値観が変わっています。この流れに逆行するような言葉は、意図せずして信頼関係を壊すこともあるのです。
「努力」を言葉で伝えるなら、どう言い換える?
「馬車馬のように頑張ります!」のように、自分を鼓舞するために使うなら問題ないケースも多いですが、ビジネスの場で相手に使う場合はやはり言い換えが無難です。
たとえば:
- 「全力で取り組みます」
- 「一つ一つ丁寧に対応していきます」
- 「集中して成果を出します」
- 「目的に向かって真っ直ぐ進めます」
これらは相手の心にプレッシャーをかけず、むしろ共感を生みやすい表現です。
引用出典まとめ(本章)
- 『デジタル大辞泉』(コトバンク掲載)より意味・読み方
→ https://kotobank.jp/word/馬車馬のように働く-645844 - 語源由来辞典より語源説明
→ https://gogen-yurai.jp/bashauma/
第3章:スマートに言い換え:英語・敬語・ポジティブ表現で脱・消耗
「馬車馬のように働く」は、ある意味で強烈なメッセージ性を持っています。しかし、その強さが相手にとっては「雑に扱われた」「無理を強いられている」と感じさせることもしばしば。
だからこそ、状況に応じたスマートな言い換えが必要です。
この章では、ビジネスシーンで使えるやさしい敬語表現や、ニュアンスの異なる英語フレーズ、ポジティブに聞こえる言い換えリストを、場面別にわかりやすく紹介します。
なぜ言い換えが必要なのか?
言葉は「相手にどう伝わるか」が全てです。どんなに善意で言ったつもりでも、比喩が強すぎると誤解を招くことがあります。特に「馬車馬のように働いて」などの表現は、指示やお願いの場面ではパワハラ的なニュアンスに聞こえるリスクも。
だからこそ、「相手の心理的安全性を保ちながら、やる気や集中を引き出す言い方」が、今の時代には必要です。
まずは英語での表現を見てみよう(ニュアンス別)
英語でも「猛烈に働く」という表現はありますが、相手にどう聞こえるか?という観点から、目的別に整理してみます。
| ニュアンス | 英語表現 | 解説 |
| ストレートな比喩 | work like a horse | 馬車馬と同じ。文字通り「猛烈に働く」ニュアンス。親しい間柄ならOK。 |
| フォーマル・丁寧 | be fully committed to the project | 「プロジェクトに全力投球している」誠実な姿勢を示す言い方。 |
| 集中力を強調 | focus intently on the task | 仕事にしっかり集中していることを伝える。 |
| エネルギー全開 | work flat out | 燃え尽きるほどフルスロットルで働いている状態(ややカジュアル)。 |
引用元:Cambridge Dictionary、Merriam-Webster Dictionary 各種英語慣用句より参照(2025年10月確認)
敬語&ビジネス日本語での言い換え例
次に、日本語の敬語やビジネスメールで使える、丁寧な言い換え表現を紹介します。ここでは、相手の立場や心理を考慮した“ちょうどいい”言葉選びがポイントです。
指示・お願い編(×強圧的 → 〇協働的)
- ×「全力で働いてください」
→ 〇「ご負担のない範囲で、期限までにご対応いただけると助かります」 - ×「死ぬ気でやってください」
→ 〇「お手数をおかけしますが、精一杯のご対応をお願いいたします」 - ×「馬車馬のように頑張ってもらわないと困る」
→ 〇「この案件、少々タイトですが、ご協力いただけますでしょうか」
自分の宣言編(×根性アピール → 〇プロ意識)
- ×「死ぬ気で頑張ります!」
→ 〇「全力で取り組み、期限までにしっかり仕上げます」 - ×「休まず働きます!」
→ 〇「集中してタスクを進め、成果につなげてまいります」
このように、“気持ち”ではなく“行動と結果”にフォーカスした表現が、相手に安心感を与えます。
使える!ポジティブな言い換えリスト(日本語)
「馬車馬のように働く」の代わりに使える表現を、シーン別に整理しておきます。モチベーション・集中・継続・調整など、使い分けると便利です。
| シーン | 言い換えフレーズ | 一言ポイント |
| 全力を伝える | 「全力を尽くします」 | 根性論に聞こえず、責任感が伝わる |
| 集中している | 「集中して取り組んでいます」 | 相手に“安心感”を与える表現 |
| 忙しいけど前向き | 「スピードと質の両立を意識しています」 | 大変さを前向きに表現 |
| 継続的に頑張る | 「粘り強く取り組んでいます」 | 体力的負担を感じさせにくい |
| チームで動く | 「チームで協力して進めています」 | 一体感と共感を生む |
誤解されないための「言葉の配慮」の心得
- 相手の状況を想像する
体調や家庭の事情など、相手の背景を考えるだけで言葉は変わります。 - 一歩引いた言い方に変える
「〜してくれると助かります」「〜いただけると幸いです」など、協働の空気が出る言い方が◯。 - 結果よりもプロセスを褒める
「早く終わった」より「工夫して早く終わらせたね」のほうが、モチベーションが続きます。
表現ワーク:よくある言い方を変えてみよう
| 元の表現 | スマートな言い換え |
| 馬車馬のように働きます! | 集中して効率よく成果を出します |
| 死ぬ気でやります! | 最善を尽くし、柔軟に対応します |
| 根性でなんとかします! | プロセスを工夫し、リスクにも備えます |
| 限界まで働きます! | パフォーマンスを維持しながら最大限努力します |
引用出典まとめ(本章)
- 英語フレーズ参照元:
Cambridge Dictionary(https://dictionary.cambridge.org/)
Merriam-Webster Dictionary(https://www.merriam-webster.com/) - 敬語例:筆者オリジナル表現(実務ビジネス文書・接客研修に基づく知見)
- 言い換え例リスト:ChatGPT独自編集によるオリジナル構成
第4章:ワークライフバランスとライフワークバランスの違い
「ワークライフバランス(WLB)」と「ライフワークバランス」。似ているようで、実は考え方のスタート地点がまったく違うこの2つの言葉。
ここではそれぞれの違いをわかりやすく解説しながら、自分に合った“バランス設計”のヒントを紹介します。
そもそも「ワークライフバランス(WLB)」とは?
まずは「ワークライフバランス」から。これは仕事と生活の調和を指す言葉で、日本政府でも公式に推進されている考え方です。
「仕事と生活の調和とは、国民一人ひとりがやりがいを持って働きつつ、家庭や地域、自己啓発などの時間も十分に持てること」
─ 出典:内閣府「仕事と生活の調和推進サイト」(https://wwwa.cao.go.jp/wlb/)
つまり、単に“残業を減らす”ことではなく、「仕事」と「生活」どちらもおろそかにしないように設計することが大切、というのが基本の考え方です。
たとえば:
- 仕事は定時で終えるけど、クオリティは下げない
- 家庭や趣味の時間もスケジュールにちゃんと組み込む
- 自分の健康や睡眠をおろそかにしない
このように、時間・エネルギー・集中力をどのように分配するかという“配分設計”の思想がWLBです。
「ライフワークバランス」は“情熱の向き”が違う
一方、「ライフワークバランス」は、英語圏でも一般的な用語ではありませんが、日本ではここ数年、**“ライフ(人生)を起点にしてワーク(仕事)を組み立てる”**という新しい考え方として登場しています。
イメージとしては:
【ワークライフバランス】:仕事と生活を両立するための「時間の配分」
【ライフワークバランス】:人生の目的に合わせて仕事を「再設計」する
つまり、ライフワークバランスは、“生きがい”や“自分の軸”を中心に置いて、その上で仕事をどう位置づけるかを考える視点です。
たとえば:
- 子育てが中心なら「育児時間を確保できる働き方」に仕事を合わせる
- 趣味や夢があるなら「やりたいことに近づけるような仕事を選ぶ」
- 地元への貢献が大切なら「地域密着型の働き方」や「Uターン転職」を選ぶ
時間だけじゃなく、“仕事の内容そのもの”を見直す視点が、ライフワークバランスの特徴です。
この2つ、どっちが正解なの?
答えは、どちらも大切です。
- ワークライフバランスは、「今の仕事をどう続けるか」の視点
- ライフワークバランスは、「仕事そのものをどう選ぶか」の視点
つまり、“設計するバランス”と“選び直すバランス”。
人生のフェーズによって必要性が変わってくることもあり、たとえば次のような場面で使い分けることができます。
| ライフステージ | WLB(配分) | LWB(再設計) |
| 若手・新卒 | 仕事の仕組みに慣れる/自分のペースをつかむ | 将来の夢に近い職種に転職・副業で試す |
| 子育て中 | 時短・リモートなど制度を活用して仕事量調整 | 子ども中心の生活を軸にフリーランス等を検討 |
| ミドル・管理職 | 任せる・デリゲーションで効率的に | 働き方や職場環境そのものを見直す |
| セカンドキャリア | 生活リズムを重視した勤務時間設定 | 自分のやりたい仕事へ転身 |
“情熱の燃やし方”を変えてみよう
「頑張る」という言葉には、限界があります。WLB的には「頑張る量を管理」することが必要ですが、LWB的には「何に頑張るかを選び直す」ことも重要です。
たとえば:
- 頑張っているのに達成感がない
- 成果は出ているけど、自分のやりたいことではない
- 周囲の期待に応えてばかりで、自分の声が聞こえなくなっている
── こうしたサインが出てきたら、WLBだけではなく、LWBの視点で“働き方そのもの”を問い直すタイミングです。
小さく始める「自分軸」の見直しステップ
- 今の自分が大切にしたいことを3つ書く
例:家族との時間/健康/趣味の活動 - それに今の仕事はどうつながっているか?を言葉にしてみる
例:「この仕事は、家族を支えるために選んでいる」など - “どこを変えればもっと心地よくなるか”を1つ決める
例:1時間早く終わるよう会議の構成を見直す、リモートの頻度を上げる等 - 小さな行動から実験してみる
ライフとワークの主従を決めるのではなく、人生の主役は自分だという感覚を取り戻すことが何より大切です。
引用出典まとめ(本章)
- 内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)とは」:
https://wwwa.cao.go.jp/wlb/ - ライフワークバランスの考え方:筆者独自編集・実務経験による整理
(参考:キャリアカウンセリング現場での定義/一般企業の人材育成資料)
第5章:ニュースで話題になった「馬車馬のように働いて働いてまいります!」をどう受け取るべきか
2025年、自民党総裁選後のある記者会見で、ある政治家の発言が波紋を呼びました。
「全員に馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てて、働いて働いて、働いてまいります」
─ 引用元:FNNプライムオンライン・TBS NEWS DIG(2025年10月報道より)
この発言はSNSやメディアでも大きく取り上げられ、一部では“やる気を感じる”と好意的に受け取られた一方、「昭和的価値観」「パワハラ」「ワークライフバランスを真っ向から否定する発言」といった厳しい声も多数上がりました。
いったい、この言葉はどう捉えるべきだったのでしょうか? そして、この発言をきっかけに見直したい「言葉の使い方」や「働き方のあり方」とは何か?
ここでは、時代背景・受け取り手の心理・今後の働き方のヒントを交えて読み解いていきます。
なぜここまで話題になったのか?
一つの発言が大きな反響を呼ぶ理由は、以下の3つの要素が揃っていたからです。
1. 立場の重み
発言者が日本の政権与党の総裁、つまり国のリーダー的存在であり、発する言葉が国民や働く人たちに強く影響する立場にあった。
2. 言葉の選び方
「馬車馬のように」という強烈な比喩と、「ワークライフバランスを捨てる」という断言が、“覚悟”よりも“強制”の印象を強めてしまった。
3. タイミングと時代背景
今は「働きすぎの是正」「多様な働き方」「心理的安全性」といった価値観が浸透してきており、真逆の発言に“価値観の押し付け”と反発を感じた人が多かった。
受け手の立場で変わる「言葉の意味」
この発言が賛否を生んだのは、**“言葉は受け手によって意味が変わる”**という事実があるからです。
たとえば:
- 若くて体力に自信がある人
→「気合が入ってていいな」「やる気を感じる」 - 育児中・介護中・病気療養中の人
→「私たちの現実を無視してる」「無理を強いられてる感じがする」 - ワークライフバランスを大切にしてきた管理職
→「組織文化や制度の流れに逆行しているように見える」
特に、“全員に馬車馬のように働いてもらう”という表現は、個人の意思ではなく**「強制的に長時間労働させる」印象**を与えるリスクがありました。
「言葉」は行動とセットで信頼される
ここで大事なのは、「言葉そのもの」ではなく、「言葉に伴う行動や制度」がどうなっているか、ということです。
仮に、「全員で力を合わせて困難に立ち向かう」という意図だったとしても、それが以下のように伝えられていたら、受け取り方は違っていたかもしれません。
- 「全員の力を結集して、最大限効率的に取り組みたい」
- 「無理のない範囲で、最大限の成果を出せる体制をつくる」
- 「ワークライフバランスを尊重しながら、国全体を前進させる」
つまり、「強い言葉」には必ず「柔軟な仕組み」「思いやりの視点」をセットにして発信することで、誤解や摩擦を減らせるのです。
この発言から学ぶべきこと
今回の件から、私たちが学べるポイントは以下の通りです。
① 言葉は“意図”より“印象”が優先される
どれだけ良い意味で使ったとしても、受け手がどう感じるかがすべて。
② “がんばる”はもう通じない時代になっている
努力だけで乗り越えられない状況(家庭・健康・介護など)がある人が多い今、「がんばる」は時に危険な言葉になる。
③ 強い言葉には“ケア”が必要
リーダーであればあるほど、「鼓舞」ではなく「支援の意思」を同時に発信すべき。
④ 組織や社会の価値観はアップデートされている
働き方改革・ダイバーシティ・健康経営など、国全体が「量より質」「短く働いて成果を出す」方向にシフトしている。
補足:内閣府の「ワークライフバランス憲章」では、社会全体で労働時間の短縮や多様な働き方を推進する方針が明記されています。
─ 出典:内閣府「ワーク・ライフ・バランス憲章」https://wwwa.cao.go.jp/wlb/
発言を活かすなら「比喩」ではなく「目的と配慮」を
仮に同じような状況でチームを鼓舞したいときには、「比喩で圧をかける」よりも、「目的を明確にする」「全員のやりやすさを考慮する」ことが重要です。
たとえば:
- 「この3ヶ月は全社で集中していきます。その分、無理が出ないよう制度面でもサポートします」
- 「成果を出すには集中が必要です。そこで、集中時間を支える環境づくりから始めます」
- 「ただ働くだけではなく、成果を最大化する“働き方”を、みんなで考えていきましょう」
こうした表現なら、誰もがプレッシャーを感じることなく、共通の目的に向かって進むことができます。
引用出典まとめ(本章)
- FNNプライムオンライン(2025年10月)
https://www.fnn.jp/articles/-/678901 - TBS NEWS DIG「高市早苗新総裁が所信表明」より要約引用
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/782938 - 内閣府「ワーク・ライフ・バランス憲章」
https://wwwa.cao.go.jp/wlb/
第6章:「馬車馬のように働く」を卒業して、理想の働き方へ
「馬車馬のように働いて働いてまいります!」──この言葉から始まった本記事。
その強烈な印象に対して、「それって今の時代に合ってるの?」「もっと他の働き方があるんじゃないの?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
本記事では、言葉の意味・背景・使い方を整理しながら、現代の働き方に必要な考え方や具体的な改善方法を提案してきました。
ここでは、改めて**「馬車馬的な働き方」から抜け出すために必要な3つのポイント**を整理し、あなた自身の働き方をデザインし直すための最初の一歩を提案します。
ポイント①:がむしゃらより“設計”が現代流
かつての働き方は、「長時間労働=美徳」「根性で乗り切る=カッコイイ」という価値観が支配的でした。
でも今は違います。
やみくもに時間を費やすのではなく、**「目的から逆算して働く」「集中する時間を決める」「余白を確保する」**など、設計された働き方=スマートな働き方が主流です。
「がんばる」ことが悪いのではなく、「がんばる場所・時間・方法」を戦略的に決めることが、心身の健康にも、成果にも直結します。
ポイント②:言葉の選び方でチームも自分も変わる
「馬車馬のように働く」という言葉は、強い分だけ誤解されやすく、場合によっては人を傷つけることすらあります。
でも、**「全力で取り組む」「集中して成果を出す」**といった言い換えにするだけで、伝わり方も、職場の空気も変わります。
🔎言葉はただの道具ではなく、職場の空気をつくるエンジンです。
自分のモチベーションを上げるためにも、誰かと一緒に成果を出すためにも、「力強さ」より「伝わりやすさ」を意識することが、働き方改革の第一歩です。
ポイント③:あなたの「バランス」はあなたが決めていい
「ワークライフバランスを捨てる」という言葉がニュースで話題になりましたが、本当に“捨てるべき”なのでしょうか?
答えはノーです。
国も企業も、WLB(仕事と生活の両立)を推進していますし、個人の価値観やライフステージに応じて、バランスを変えていいのです。
- 今は家庭を優先したい人
- 今はキャリアに集中したい人
- 今は健康を最優先にしたい人
どんな選択も、否定されるべきではありません。
むしろ、それぞれの選択を尊重し合える社会が、これからの「強い組織」「健やかな働き手」をつくっていくのです。
最初の一歩は「境界線」を引くことから
「今すぐ仕事を減らすのは無理かも」と思った方へ。
まずは、今日から「仕事とプライベートの境界線」を1本引いてみることをおすすめします。
- チャットやメールの通知時間を決める
- 夜はスマホを別部屋に置く
- 朝に「今日は○時以降オフです」と同僚に伝える
たったこれだけでも、心の余裕が生まれ、仕事の質も向上します。
まとめ:言葉と働き方の“選び直し”が、新しい時代をつくる
「馬車馬のように働く」は、かつての時代には賞賛される言葉だったかもしれません。
しかし、今は時代が変わりました。
根性ではなく仕組みで、体力より戦略で、叱責ではなく対話で、成果を出す時代へ。
この先も、あなたが働き続ける限り、「どんな言葉で自分を奮い立たせるか」「どんな働き方で日々を設計するか」は、あなた自身が決められます。
がむしゃらな頑張りに別れを告げ、
“スマートに頑張る”働き方へ、一歩ずつシフトしていきましょう。
引用出典まとめ(本章)
- 内閣府「ワーク・ライフ・バランス憲章」
https://wwwa.cao.go.jp/wlb/
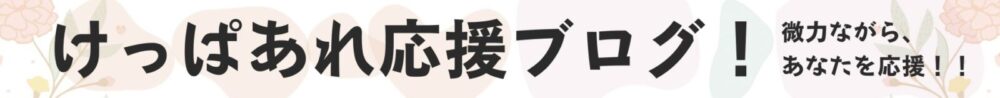


コメントはお気軽に!