2025年、自民党総裁・高市早苗氏の馬車馬のように働く「ワークライフバランスを捨てる」発言がSNSを中心に大きな議論を呼びました。「働き方改革」が進んできたはずの日本で、なぜ今そんな言葉が出てきたのか?本当に「捨てるべき」ものなのか?
この記事では、ワークライフバランス(WLB)の基本から、その欠点や誤解、そして代替となる「ライフワークバランス」の新たな考え方までを、わかりやすく解説します。
今、「仕事と人生のバランス」は岐路に立っています。
あなたは、人生馬車馬 のように働きますか?
なぜ高市早苗の“ワークライフバランス捨てる”宣言が炎上したのか?
2025年、自民党総裁選で勝利した高市早苗氏が語った「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます」という発言が、SNSやメディアで大きな波紋を呼びました。「働いて、働いて、働いて…」と繰り返したその言葉は、まるで昭和の“根性論”のようだと受け取られた人も多かったのです。
一部の人は「日本人の勤勉さを取り戻そうとしている」として支持しましたが、多くの人は「もうそんな時代じゃない」「ワークライフバランスを軽んじてはいけない」と批判しました。背景には、コロナ禍を経て「働き方」を見直したいという世間の空気があります。
この発言は、高市氏が“個人の覚悟”として語ったものですが、国のリーダーが発信した言葉だけに、国民全体への強いメッセージと受け取られてしまったのです。
※参考文献 Yahoo!ニュース
高市早苗の「ワークライフバランスを捨てる」発言は実に巧妙だ 安倍晋三の功績を汚すのか、称えるのか
WLB(ワークライフバランス)って何?
「WLB」とは「Work-Life Balance(ワークライフバランス)」の略で、仕事と生活のバランスを大切にする考え方です。仕事にばかり時間やエネルギーを使いすぎず、家族・趣味・健康・学びなど“人生のほかの部分”にも目を向けよう、というものです。
昔の日本では「長時間働くことが美徳」とされていましたが、現在は、働きすぎが原因でうつ病や過労死が起きることもあるため、「働きすぎはよくない」と見直されてきています。
企業も政府も、社員の満足度や健康を守るために「働き方改革」を進めてきた中での、「WLBを捨てる」発言だったため、大きな注目を集めたのです。
国民に影響は?働き方の未来はどうなる?
高市氏の発言をきっかけに、「また昔のように働かされるのでは?」と不安に感じた人も少なくありません。特に、若者や子育て世代、介護と両立して働く人にとって、WLBは「生きるために必要な制度」とも言える存在です。
もしも政府や企業が「もっと働け」という流れに傾けば、そういった人たちの生活や精神的なゆとりが奪われる可能性もあります。
しかし逆に、「高市氏の言葉が、仕事に対する誇りを思い出させた」という声もあります。つまり「働くことに本気で向き合おう」というメッセージだと捉えれば、モチベーション向上のきっかけになるとも考えられます。
私たちは、社会の空気に流されすぎず、自分自身の働き方を自分で選ぶ力がますます求められる時代に入っているのです。
SNSの反応から見える「時代の分かれ目」
高市氏の発言に対するSNSの声は、まさに「賛否両論」。ある人は「頑張ることを否定する社会はおかしい」とし、また別の人は「ワークライフバランスを軽んじると、過労死が増える」と危機感をあらわにしました。
このような反応の分かれは、「昭和的な価値観」と「令和的な価値観」のぶつかり合いを象徴しているとも言えます。
つまり、昔ながらの「仕事がすべて」「働くことこそ正義」という考えと、今どきの「自分の人生を大切にしたい」「無理せず働きたい」という考えが、社会全体でせめぎ合っているのです。
これは“時代の分かれ目”。これからの日本がどちらの方向へ進むのか、国民一人ひとりが「自分の意見を持つこと」が大切になります。
発言の裏にある“政治的メッセージ”とは?
実は、高市氏の発言は「ただの気合い」ではなく、かなり計算された“政治的メッセージ”とも考えられます。
彼女が掲げる「強いリーダーシップ」や「本気で改革を進める」という姿勢を、短く強い言葉でアピールするために、あえて刺激的なフレーズを使った可能性もあります。
また、党内に存在する「働き方改革はもうやめよう」という保守的な意見に呼応する意味も含まれているという見方もあります。
このように、一見すると過激にも思える発言の裏側には、戦略的な意図がある場合もあります。ただし、言葉の受け取り方は人それぞれ。だからこそ、言葉の使い方には十分な注意が必要です。
「ワークライフバランスなんて幻想だ」?日本社会が抱える根深い課題
日本でWLBが進まない本当の理由
日本では、政府が「働き方改革」や「ワークライフバランス推進」といった政策を打ち出してきましたが、実際にはなかなか浸透していないのが現実です。その大きな理由の一つが、「働きすぎを美徳とする文化」です。
「遅くまで残業する人がえらい」「有給をとらないのががんばっている証拠」などの価値観が、今も多くの職場に根付いています。上司が帰るまで部下が帰れない風土や、長時間労働を当然とする風潮は、ワークライフバランスの実現を邪魔しています。
また、中小企業では人手不足のため、制度を整える余裕すらない場合もあります。つまり、「仕組みの問題」だけでなく、「文化と現場の現実」が大きな壁になっているのです。
3つの立場(企業・政府・個人)でのギャップ
ワークライフバランスを実現するには、企業・政府・個人の3者が協力する必要がありますが、それぞれに意識のズレがあります。
| 立場 | 理想 | 現実の悩み |
| 企業 | 優秀な人材を長く働かせたい | 生産性や利益とのバランスに苦しむ |
| 政府 | 少子化・介護問題対策にWLB推進 | 法制度と現場の乖離が大きい |
| 個人 | 仕事も人生も大事にしたい | 会社に言い出せず、我慢が続く |
このようなギャップを埋めるには、「対話」と「制度」と「意識改革」がすべて必要です。どれか一つが欠けても、ワークライフバランスは絵に描いた餅になってしまいます。
「働き方改革」は何だったのか?
「働き方改革」という言葉が流行ったのは、2017年ごろ。長時間労働を減らすための法改正や、テレワークの導入が進みました。とくにコロナ禍ではリモートワークが急増し、「時間や場所に縛られない働き方」が現実のものとなりました。
しかし、その一方で「仕事とプライベートの境目がなくなった」「むしろ家でも休めなくなった」という声も出てきました。また、現場の上司が古い価値観を持っていると、制度があっても使いにくいというケースも少なくありません。
つまり、制度だけ整えても「働きやすい社会」にはならないのです。重要なのは、制度の“使いやすさ”と、企業文化や職場風土の変革なのです。
WLBの欠点と現場のリアル
ワークライフバランスは、たしかに素晴らしい考え方ですが、現場では「使いにくい」「逆に気をつかう」という声もあります。
例えば、時短勤務や在宅勤務をしている人が「他の人に迷惑をかけていないか」とプレッシャーを感じてしまったり、「休みを取ると評価が下がる」と思ってしまったり。
また、働き方を柔軟にすると「自己管理」が重要になりますが、それがうまくできず逆にパフォーマンスが下がってしまう人もいます。
つまり、WLBには「制度の整備」だけでなく「風土づくり」と「人材育成」がセットで必要なのです。
「成果主義」との相性の悪さ
最近では「成果主義」が多くの企業で取り入れられていますが、これがWLBとぶつかることもあります。
なぜなら、成果主義では「どれだけ頑張ったか」より「何を達成したか」が重視されます。すると、働く時間を減らしたとしても成果が出せれば問題ないのですが、現実は「成果を出すには結局、長く働かざるを得ない」というジレンマに陥りがちです。
また、「成果が見えにくい仕事」や「チームでの成果」が評価されにくくなることもあり、チームの協力より“個人プレー”が増えてしまうリスクもあります。
このように、ワークライフバランスは素晴らしい考えである一方で、実現のためには「制度」「文化」「評価」のすべてを見直す必要があるのです。
ライフワークバランスという考え方がじわじわと注目されている理由
ワークライフバランスとの違いとは?
「ワークライフバランス(WLB)」とよく似た言葉に「ライフワークバランス(LWB)」があります。文字の順番が違うだけのように見えますが、考え方はまったく異なります。
ワークライフバランスは「仕事」と「生活」を分けて、それぞれのバランスをとることを目指します。たとえば「平日はしっかり働き、週末はしっかり休む」という考え方ですね。
一方、ライフワークバランスは「人生の一部としての仕事」という発想です。つまり、「人生全体が充実するような働き方をしよう」というスタンス。仕事も生活も対立せず、どちらも自分らしさを表す一つの手段としてとらえるのです。
この違いを図で見てみましょう。
| 概念 | 意味 | 働き方のイメージ |
| ワークライフバランス | 仕事と生活の“バランスを取る” | 分けて考える(on/off) |
| ライフワークバランス | 人生の中に“仕事を組み込む” | つながっている(融合) |
ライフワークバランスは、特に「やりがい」や「自分らしさ」を大事にする世代に支持されており、今後ますます注目されていくでしょう。
「やりがい」と「自分らしさ」を軸にした働き方
ライフワークバランスが注目されている背景には、「ただお金のために働く時代は終わった」という時代の流れがあります。人々は今、「自分らしく生きる」ことや、「やりがいのある仕事をしたい」と思うようになってきています。
たとえば、ある人は「社会に貢献できる仕事をしたい」と思うかもしれませんし、別の人は「趣味を活かした仕事をしたい」と考えるかもしれません。つまり、収入だけでなく「心の満足感」や「成長感」が重要視されているのです。
また、SNSやYouTubeのような発信の場が広がったことで、自分の「価値観」や「働き方」を他人と比較する機会が増え、「自分はどうありたいのか?」という問いが生まれやすくなっています。
仕事は人生の大部分を占めるからこそ、やりがいと自分らしさを両立できる働き方を選びたい、というニーズが高まっているのです。
海外の事例に学ぶ“人生と仕事の調和”
ライフワークバランスは、ヨーロッパを中心に多くの国で取り入れられています。特に注目すべきは、スウェーデンやデンマークなど北欧諸国の取り組みです。
たとえばスウェーデンでは、「6時間労働制」を導入した企業もあります。これは「短い時間で高い成果を出す」ことを前提にしており、家庭の時間や趣味の時間を大切にする文化が根付いています。
デンマークでは「フレックス制度」が進んでおり、子どもを迎えに行くために早退することが当たり前。仕事だけでなく“家族との時間”が社会全体で大切にされています。
こうした国々では、単なる制度改革だけでなく、「人生をどう生きるか」という哲学が根付いています。私たち日本人も、こうした事例から「働くとは何か?」をもう一度考え直すヒントが得られるはずです。
フリーランスや副業時代の新しい考え方
いま、働き方はどんどん多様化しています。会社に所属せずに働く「フリーランス」や、会社員を続けながら別の仕事もする「副業」が当たり前になってきました。
このような時代では、自分の時間をどう使うかがより自由になります。会社が決めた時間ではなく、自分で「今日はどれくらい働くか」「どの仕事をするか」を選べるようになるのです。
ただし、自由には責任も伴います。だからこそ、「自分はどう生きたいのか」「どんな働き方が自分に合っているか」を考える必要があります。これがまさにライフワークバランスの視点です。
好きなことを仕事にする、複数の仕事をバランスよくこなす、自分のペースで働く——これからは、そんな“新しい働き方”がますます広がっていくでしょう。
高市発言から見える、ライフワークバランス時代の到来?
高市早苗氏の「WLBを捨てる」発言は、多くの人にとってショックでした。しかし、それがかえって「じゃあ自分はどう働きたいのか?」と考えるきっかけになったとも言えます。
ワークライフバランスは、どちらかというと「会社に整えてもらう制度」でした。一方、ライフワークバランスは「自分で選ぶ働き方」。つまり、もっと“自立した視点”が必要なのです。
これからの時代は、「会社に合わせる」だけではなく、「自分の人生設計に合わせて働き方を選ぶ」ことが求められます。高市氏の発言がある意味で“揺さぶり”になったことで、多くの人がその変化に気づき始めたのではないでしょうか。
もしも「ワークライフバランスを理由に辞めたい」と思ったら?
本音と向き合うための自己分析
「もう限界。ワークライフバランスがとれない…」
そんなふうに感じたとき、まず大切なのは「本当の理由」を自分でしっかり見つめ直すことです。
本当に辞めたい理由は、仕事の内容ですか?人間関係?働く時間?それとも、自分の理想とのギャップ?
自己分析のポイントは次の3つです。
- 仕事の何が一番つらいのか書き出す
- 理想の一日の過ごし方を想像してみる
- その理想に近づくために何が必要か考える
このステップを踏むと、「辞める前にできることはないか?」という視点も持てます。勢いで辞めてしまう前に、自分の“心の声”に耳を傾けることが、納得のいく選択への第一歩です。
辞める前に試す“環境調整術”
退職を決意する前に、一度「環境を変える」ことを検討してみてください。たとえば:
- 上司に相談して業務を見直してもらう
- 部署異動や働き方(時短・在宅)の変更を申し出る
- 心身のケアとして、有給や休職制度を使う
意外と、周囲に話してみたら協力してもらえることもあります。「甘えだと思われるかも…」と心配になる気持ちはわかりますが、自分を守るのは自分しかいません。
また、信頼できる同僚や家族に話すだけでも心が軽くなることがあります。「辞める」以外の選択肢もあることを忘れずに。
退職理由として伝えるときのポイント
いざ辞めることを決めたとしても、会社に伝えるときは慎重に。特に「ワークライフバランスが悪いから」という理由をそのまま伝えると、場合によっては角が立つこともあります。
そこでおすすめの伝え方は、
- 「これ以上無理をすると体を壊すと感じた」
- 「自分の人生の方向性を見つめ直したい」
- 「より柔軟な働き方をしたいと思うようになった」
というように、「前向きな理由」と「感謝の気持ち」をセットで伝えること。すると、退職後も円満な関係を保ちやすく、次の仕事への影響も少なく済みます。
家族やパートナーとの話し合い方
退職は、自分だけでなく家族やパートナーにも影響する大きな決断です。収入が減る可能性や生活リズムの変化があるため、話し合いは丁寧に行いましょう。
ポイントは3つ:
- 正直な気持ちを隠さずに話す
- 感情的にならず冷静に説明する
- 今後の生活プランも一緒に考える
一人で抱え込まず、「味方」を増やすことが大切です。特に共働き家庭や子育て世代では、働き方の変化は家族全体に関わる問題なので、みんなで乗り越えていく姿勢が必要です。
「辞めたあと」の人生設計の考え方
退職はゴールではなく、新しい人生のスタートです。辞めたあとに「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、次のステップをしっかりイメージしましょう。
考えておきたいこと:
- 生活費や貯金の計画
- 転職活動の準備とスケジュール
- 新しい働き方(副業、起業、学び直しなど)
さらに、「自分にとっての幸せとは何か?」をじっくり考える時間も大切です。辞めることで、ようやく“本当の自分”に向き合える人もいます。
「ワークライフバランスを理由に辞める」は、決して悪いことではありません。大切なのは、自分の人生を自分で選ぶこと。勇気ある決断は、きっと次の扉を開いてくれます。
「メリハリのある働き方」を実現する具体的な方法
時間管理と集中力アップのコツ
「仕事が終わらない…」「1日があっという間に過ぎる…」と感じたことはありませんか?
それは、時間の使い方に“ムダ”があるサインかもしれません。
時間管理で大事なのは「やるべきこと」と「やらないこと」をハッキリさせること。たとえば…
- 朝一番に「今日やること」を3つだけ決める
- タスクを25分集中・5分休憩の「ポモドーロ法」で区切る
- 会議や打ち合わせは「時間を決めて」「目的を明確に」
また、「ながら作業」は集中力を下げる原因。スマホは通知を切っておく、BGMは歌詞のないものにするなど、集中できる環境づくりもポイントです。
仕事を早く終わらせることは「サボり」ではなく、「効率的に成果を出す」ための賢い選択なのです。
仕事とプライベートを分ける人の特徴
「メリハリある働き方」をしている人の共通点は、“オンとオフのスイッチ”を上手に切り替えられることです。
たとえば…
- 仕事が終わったらパソコンをシャットダウンして机を片づける
- 服装を変えて“オフモード”に入る
- 通勤時間を「気持ちの切り替え」に使う(リモートなら、散歩など)
また、プライベートの時間には仕事のことを考えないように意識するのも大切。休日でもSlackを開いてしまう、メールをチェックしてしまう…というのはNGです。
“切り替え上手”は“休み上手”。結果的に、次の仕事のパフォーマンスも上がります。
デジタルデトックスのすすめ
スマホ、パソコン、タブレット、SNS…。今の私たちは“常に何かに接続されている状態”で暮らしています。
これが疲れやストレスの原因になることも少なくありません。だからこそ、意識して“デジタルデトックス”を取り入れることが大切です。
おすすめの方法:
- 夜9時以降はスマホを触らないルールを作る
- 休日は「通知OFF」して1日過ごしてみる
- デジタルではなく、紙の本や手帳を使ってみる
スマホから離れて自然の中で過ごす時間は、心のバランスを取り戻してくれます。メリハリのある暮らしをしたいなら、“つながらない時間”を持つことも必要です。
“がんばりすぎない勇気”を持つ方法
日本人は「がんばるのが当たり前」という文化があります。でも、本当にずっとがんばり続けなければいけないのでしょうか?
「休む=悪いこと」と思ってしまうのは、自分を苦しめる原因になります。ときには「今週はちょっと手を抜こう」と言える勇気も大事です。
がんばりすぎないためのヒント:
- 自分に小さなごほうびをあげる(甘いもの、映画、昼寝…)
- できたことに目を向けて「よくやった」と認める
- 「誰かに迷惑をかけてもいい」と思ってみる(人は助け合って生きている)
“余白”があるからこそ、人は笑顔になれます。笑顔で働くためには、「がんばらない日」があってもいいのです。
「働きやすい職場」への言い換えと理想像
最近では「働きやすい職場」という言葉もよく使われますが、それをどう言い換えるかで、職場の“本音”が見えてきます。
たとえば:
- 柔軟な働き方ができる職場
- 自分らしく働ける環境
- 誰もが安心して働けるチーム
こうした表現に置き換えることで、「単に楽な仕事」ではなく、「人を大切にする職場」であることが伝わります。
理想の職場とは、制度だけでなく「人との信頼関係」や「成長できるチャンス」がある場所。自分の意見が言えて、無理なく働けて、成果も認められる。そんな環境を目指すことが、ワークライフバランスの実現につながります。
まとめ:高市早苗の「ワークライフバランスを捨てる」発言から考える、私たちの未来
高市早苗氏の「ワークライフバランスを捨てる」という発言は、たしかに衝撃的でした。しかし、その言葉は、私たちにとって「働くとは何か?」「人生と仕事のバランスとは?」を深く考えるきっかけにもなりました。
日本でのワークライフバランス推進は、制度や法整備だけでなく、文化や意識の変革が不可欠です。そして、今注目されている「ライフワークバランス」の考え方は、仕事を人生の中心に置くのではなく、自分らしい生き方の一部として捉えるスタイル。
どちらのバランスが正しいかではなく、「自分はどう生きたいか」「どんな働き方をしたいか」を自分自身で選ぶ力こそが、これからの時代に求められます。「働くこと」は人生の一部。でも、すべてではありません。
あなたにとっての“ちょうどいいバランス”を、これから見つけていきましょう。
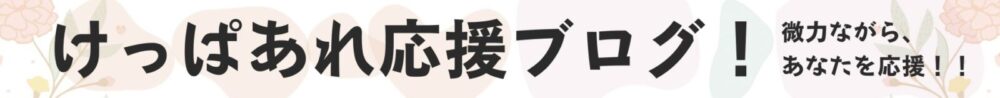


コメントはお気軽に!